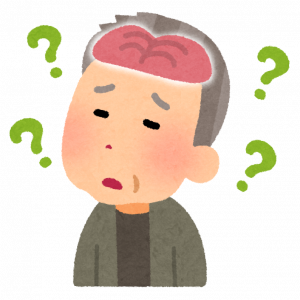認知症は「予防」するべきか問題
「認知症予防」という言葉の意味
「認知症予防」という言葉の使い方には慎重であるべき、という意見があります。
認知症(は)予防(できる)という認識が広まると、認知症になった方というのは「予防を怠った人」という誤った認識を助長することになりかねないと懸念する考え方です。私もそう思うようになりました。
そもそも認知症は予防できるのか
認知症の原因となる疾患で代表的なものとされるアルツハイマー型認知症の最大の危険因子は「年を取ること」です。誰でも長生きすればするだけ認知症になる可能性が高まるわけですね。昔と比べて認知症の方が増えているのはそれだけ私たちが長生きになったからでしょう。
つまり「昔の人は認知症になれるほど長生きできなかった」という言い方もできるわけです。
確かにテレビや雑誌、インターネット記事などで定期的に、アレを食べると良いとかコレを飲むと良いとか、脳トレがどうとか運動が良いとか認知症予防についてはいろいろ言われていますが、加齢という因子を押し返すほどのものではありません。
年齢を重ねれば誰しも身体のあちこちが衰えます。食事や睡眠に気を使い、トレーニングを重ねて昨年も大活躍した大谷翔平選手も、筋力が衰え、動体視力が落ち、ホームランを打てず三振を奪えなくなる日が必ず来るんですよね。
足から衰える人もいれば、内臓が先に衰える人もいます。目が衰えて見えづらくなる人もいれば、聴力が衰えて耳が遠くなる方もいます。認知症は衰える場所が(たまたま)脳だったということです。
認知症予防よりも大切なこと
認知症は誰だってなる、長生きになればその可能性は高まるのであれば、大切なのは予防よりも「認知症の人が周囲にいても当たり前」「いつか自分も行く道、と認知症の方と当たり前に接する」「どんなことで困るのか、何が心配なのかを知る」など、ひとりひとりが適切に認知症を理解する社会を構築することなのではないかと思います。
認知症になっても心配せずに暮らせる街で、認知症の方に必要な手を差し伸べられる地域コミュニティが構築された社会…という意識で「認知症」に向き合ってみるのも良いのではないでしょうか。


 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム